美術検定の正倉院関連の問題で、問題設定が甘い問題がありました。
次の問題は美術検定2級の問題集に掲載されている問題です。
(185) 当時、日本の意匠と高度な職人の技によって発展し、日本の法隆寺や正倉院の宝物としてもその遺品が伝えられた工芸品はどれですか。
①「白瑠璃碗」
②「銅編鐘」
③「金縷玉衣」
④「汝窯青磁水仙盆」
【解答】①
【解説】正倉院宝物には、中国・唐王朝やササン朝ペルシアをはじめ、アジア全域の文物が含まれることから、正倉院は「シルクロードの終点」ともいわれます。とりわけペルシアの玻璃器(ガラス)は、当時の高度な技術と東西交流がうかがい知れる貴重な遺品です、白瑠璃碗や瑠璃杯などいくつかの名品が正倉院に伝わります。『マークシートで学ぶ美術の歴史[中級編]美術検定2級練習問題2014』p.102,103
『知る、わかる、みえる 美術検定2級問題 応用編:intermediate』p.112,113 問191も同一の問題
この問題何を問うているのかがよく分からず、解答に苦しみます。
まずは各選択肢を検討していきます。
①の《白瑠璃碗》は正倉院宝物です。透明なアルカリ石灰ガラス製の碗で、円形の切子が亀甲文様をなしています。ササン朝ペルシアで製作されたと考えられています。
②の「銅編鐘」とは、音の高さの異なる青銅製の鐘を多数吊るした古代中国の打楽器です。
③の「金縷玉衣」とは中国の漢代の皇帝や高級貴族が葬られる時に、死者に着せた玉を金糸で綴った衣です。
④の《汝窯青磁水仙盆》とは、北宋の汝窯で焼かれた青磁の最高傑作で、台北の國立故宮博物院に所蔵されています。
②~④については、中国でしか製作されておらず、日本の奈良時代には製作されていないどころか伝来もしていないですから全くの誤りです。以下では①「白瑠璃碗」について考察します。
次に問題文中の「日本の法隆寺や正倉院の宝物としてもその遺品が伝えられた工芸品」について考察していきます。
《白瑠璃碗》の作例として有名なものは次の2点です。
(1) 正倉院宝物の《白瑠璃碗》中倉68 引用元:宮内庁正倉院宝物検索
https://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000011989&index=0

(2) 伝安閑天皇陵(高屋築山古墳、大阪府羽曳野市)出土の重要文化財《白瑠璃碗》(古墳時代・6世紀、東京国立博物館)

正倉院の《白瑠璃碗》が亀甲文様であるのに対して、伝安閑天皇陵出土の《白瑠璃碗》は円文が刻まれているのが異なります。
少し調べてみましたが、法隆寺所蔵の白瑠璃碗は見つかりませんでした。もし御存知の方がいらっしゃいましたら、御連絡をいただけますと大変助かります。
更に、問題文中に「当時、日本の意匠と高度な職人の技によって発展し」とありますが、奈良時代には飛鳥池遺跡(奈良県明日香村)に代表されるガラス工房が既に存在しており、鉛ガラスのガラス玉を作る技術は日本にありました。このガラス玉は正倉院宝物や法隆寺の宝物としても多数収蔵されており、東大寺三月堂《不空羂索観音立像》の宝冠にも使用されています。
しかし、《白瑠璃碗》のようなアルカリ石灰ガラスの高度なカットグラスを作る技術は日本や唐にはありませんでした。カットグラスが日本で作られるようになるには江戸時代の江戸切子や薩摩切子の登場を待たなければなりません。
読み方を変えて「日本の意匠と、(ササン朝ペルシアの)高度な職人の技術」と読んだとしても、無理があります。亀甲文様は中国から日本に伝わった吉祥文様です。古代にわざわざ日本からササン朝ペルシアの工房に亀甲文様のカットグラスをオーダーしたとは考えにくいでしょう。中国の影響を受けて制作したと考えるのが自然だと思います。
解答がもし「ガラス製品」なら国産のガラスもあったので正解になりますが、この問題文から「白瑠璃碗」を導くのは厳しいです。「正倉院の宝物」から解答を忖度させる悪問というよりも、問題文と選択肢が対応していない出題ミスだと考えています。
美術検定公式問題集の解説文にも、正倉院や正倉院のガラス器の解説はありますが、「日本の意匠」と「法隆寺の宝物」に対応する解説がなく、説明が不足しています。
美術検定問題集の全体的な問題点なのですが、解説がコラムのようになっていて解説としての役割を果たしていないものが散見されます。
また、美術検定で一度出題ミスをしてしまうのは仕方がないですが、問題集の改訂を何度経ても悪問が残り続けており、編集や校正を適切に行っているのか疑念が生じます。
入試などとは異なり趣味の検定ではありますが、題意に沿った解説や選択肢毎の吟味など親切な内容になるとより受検者にとって便利になると思います。


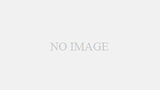
コメント