2024年の美術検定1~3級のオンライン試験が11月16日(土)、11月17日(日)に決まりました。そこで私がどのように美術検定2級の勉強をしていったかを振り返りたいと思います。
美術検定とは
美術検定とは一般社団法人美術検定協会により実施される検定で、主に西洋美術や日本美術の歴史が出題されます。4級から1級まであり、私なりの解釈ですがそれぞれのレベルは次の通りになります。
- 4級:中学校の美術や歴史の教科書に載っている内容。
- 3級:高校の美術や日本史・世界史の教科書・図説資料集に載っている内容。
- 2級:大学の教養課程で学ぶ美術史の内容。
- 1級:学芸員や美術の教員、ボランティアガイドなど、正確な美術の知識だけではなく、適切に発信出来る。
美術の背景知識は大いに越したことはありませんが、一般的には美術検定2級程度の知識があれば充分に美術鑑賞を楽しめると考えていますので、以降は美術検定2級に絞って説明します。3級や4級対策をされる方は、御自身の知識に合わせてこの内容から適宜間引けばいいと思います。
大学入試であれば西洋美術史は3級、日本美術史は2級程度の知識があれば、早慶など難関大学の世界史・日本史で出題される美術史問題でも難なく対応できます。
美術検定2級について
美術検定2級は西洋美術・日本美術に加え、現代美術や東洋美術、美術館の展示や法規など幅広い分野が出題されます。美術史問題と実践問題、それぞれ約60%の正答で合格となります。
| 形式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準 | 合格率 | |
| 美術史問題 | 選択式 | 約85問 | 60分 | それぞれ約60%の正答 | 約40% |
| 実践問題 | 選択式 | 約15問 | 30分 |
美術検定の問題は、以下で構成されます。
- 美術史問題:美術作品や作家、時代、様式、運動など美術に関する知識を問う。
- 実践問題(2級以上):美術鑑賞の場の役割や機能、現状に関する知識を問う。
- 知識・情報の活用問題:作品や資料など美術に関する情報から、総合的に判断・思考する能力を問う。
教材
- 『改訂版 西洋・日本美術史の基本』(以下 基本テキスト)
- 『続 西洋・日本美術史の基本』(以下 続・基本テキスト)
- 『アートの裏側を知るキーワード』
- 『知る、わかる、みえる 美術検定2級問題 応用編:intermediate』(以下 2級問題集)
- その他参考資料
美術史問題の勉強方法
佐藤優氏の『読書の技法』(東洋経済新報社、2012年)に書かれている世界史の勉強法を応用しました。
ポイントは次の通りです。
短期間で試験に合格するには「漆塗り」の要領で反復する事が効果的
また武田塾の「参考書を読んでいる時よりも問題を解いている時に力が付く」という考え方にも沿っています。
基本の勉強方法は次の通りです。
- 基本テキスト、続テキストの「ルネサンス」など切りのいい章を読む
- 問題集で読んだ範囲の問題を解く
- 間違えた問題をテキストなどで復習する
- 2.-3.を繰り返す
基礎知識の量や覚えやすい勉強法は人それぞれですから、この方法にアレンジを加えて自分に合った勉強法にしていってください。
私の場合は高校で世界史が必修であったのと、センター試験を日本史で受験していたので、美術検定の勉強ではその分のアドバンテージがありました。
問題集の使い方
この勉強方法で重要なのは問題集の使い方です。
最初に問題を解いた時は、間違えてもよいですし、間違えた所はこれから覚えて本番で取りこぼさないようにします。
もしこの時点で半数程度の正答率でしたら、3級の問題集を完璧にして基礎を作ってから取り組むと理解が早いと思います。この場合は夏までに集中して基礎固めをしないと本格的な2級対策の時間が取れなくなってしまうのでバランスに気を付ける必要があります。
問題を解いたら次の4段階で評価します。
◎……既に知っている事で、似たような問題が出題されても確実に正解出来る
○……正解出来たが、他の選択肢に分からないものがある
△……曖昧な知識だが、何となく正解してしまった
×……間違えてしまった
重要なのはここからの復習です。ただ採点するだけでなく、正解した問題も1周目は解説を読みます。
それから知識が曖昧な部分は基本テキストや他の本などで調べて知識を確認します。この時ハズレ選択肢の分からない箇所も復習します。例え〇だった問題でも本番では他の選択肢の内容が問われるかもしれないからです。
2周目からは問題集中心の学習にします。問題集で◎以外の問題を解き直します。その中でもう間違えないだろうという問題は◎に評価を上げます。その過程で苦手な分野があれば再度基本テキストの該当ページなどに戻り復習します。
その後は2周目と同じサイクルを何回も繰り返します。だんだん知っている内容が多くなっていくので、1周にかける時間が短くなっていきます。
私が受験した時には4周繰り返し、最後は試験の直前に1週間程度で周回しました。
他にも、得意分野は更に『西洋美術史』・『日本美術史』を読むなどしてブラッシュアップします。苦手な分野は配点割合にもよりますが最低限問題集と同じような問題が出題されたら解けるようにしておいて、失点しても全体で合格点を狙う方法もあります。
例えば東洋美術史は数問しか出題されず、問題集レベルの問題が出題されます。検定全体を考えれば東洋美術史を丹念に勉強するよりも、問題集と似たような問題は取りこぼさないようにして後の問題は割り切るのも戦略の一つです。但し、日本美術は東洋美術の影響を受けている事を考えれば勉強しないのは寂しいのですが。
美術検定は絶対評価に近い試験ですから、本番で重要な事は解ける問題を取りこぼさない事です。
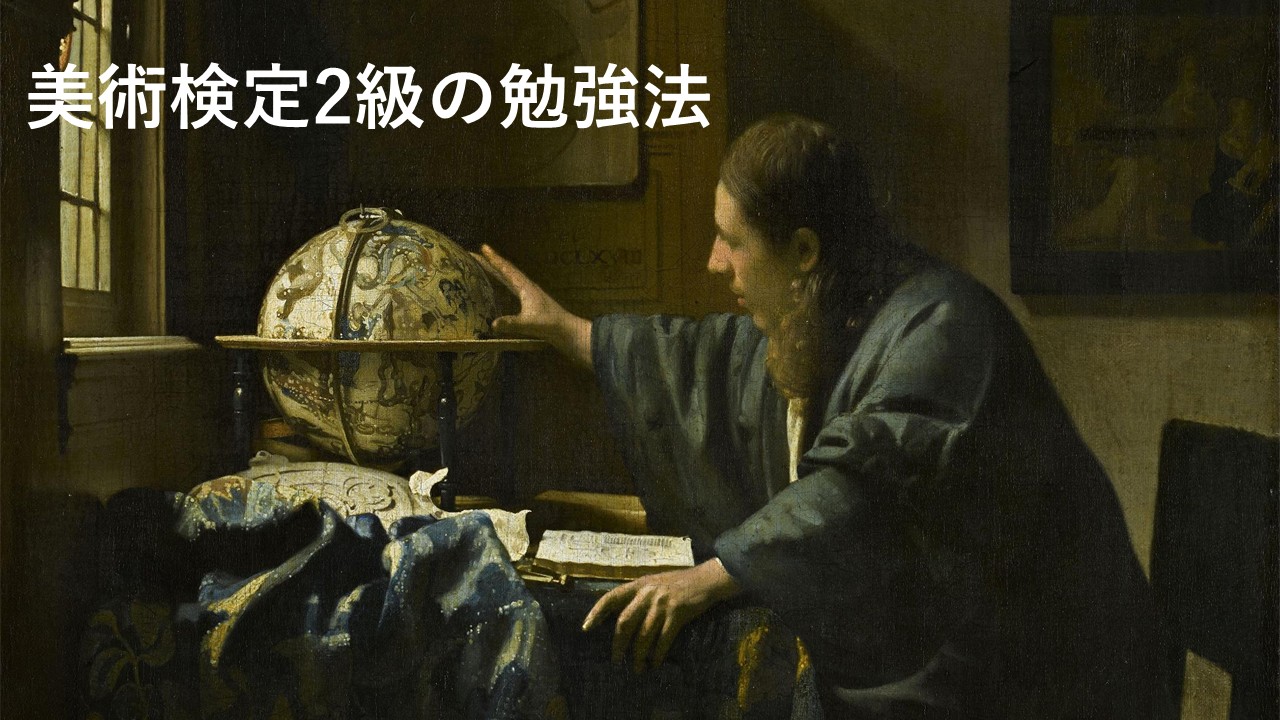

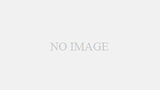
コメント