昼の部 星合世十三團 成田千本桜
昼の部は13代目團十郎の『星合十三團』でした。
普通に上演すれば丸一日かかる『義経千本桜』を半日のダイジェストにまとめ、公家荒れから武士、町人、そして狐まで、老若男女の13役を早替りを用いて團十郎一人で演じ分けるのが眼目です。
しかしながら、13代目に因んで團十郎が13役を演じる事が主眼となってしまっており、早替りとダイジェスト化のために親子や君臣の心の繋がりが見えにくいのに加え、元々不慣れな女形をはじめ演じ分けられているとは言い難い内容でした。
幕開きは福原のだんまりでした。平教経が横川の覚範に成り代わった所へ平知盛、平維盛が登場します。
その後口上になり、人物相関図を用いてあらすじの説明となります。『義経千本桜』程の名作であれば見物客も全段のあらすじを知っているのが当然ではあるのですが、観客が早替りで混乱しないようにする試みでしょう。
ここで気になったのが、平家が壇ノ浦で滅亡したと科白でも口上でも述べていた事です。『義経千本桜』では敢えて屋島の合戦で平家が滅んだ事になっています。壇ノ浦の名を出すと本当に平家が滅んだ印象になってしまい、実は平家が生き残っていたとする本作品の世界とそぐわなくなってしまうからです。『裏表太閤記』でも同様の問題を指摘しますが、史実と戯曲との関係性について考えさせられました。
さて、舞台が転換すると堀川御所になります。ここで本来「大内の段」で登場する藤原朝方が堀川御所に赴いた設定で初音の鼓の下賜と平家残党詮議の命令があり、普段は滅多に上演されませんが全体の筋が分かりやすくなります。團十郎の朝方は公家荒れの凄みのある芝居であり、今回の13役の中では良い部類に入ります。梅玉休演のため松也の代役でした。
「堀川御所の段」になりますが、團十郎の卿の君、不慣れな女形ですが思ったよりはぎこちなさが無かったです。卿の君と義経との情愛の描き方が薄く、卿の君の自害、川越太郎の親子の告白、介錯と取り敢えず筋を通します。
「鳥居前」の前段は省略され、芋洗いの弁慶から着想を得た土佐坊海尊を討ち取る場面が加わります。雀右衛門の静御前が縛られたところで逸見藤太、團十郎の佐藤忠信が登場し立ち廻りになります。
「渡海屋」の銀平の出では傘をさして下駄を鳴らしスケールが大きく、見応えがありました。しかし、知盛の舞は省略されており、安徳帝と知盛との情愛が伝わりません。
「奥座敷」では團十郎の入江丹蔵が相討ちとなった後、魁春の典侍の局と安徳帝が入水しようとするまでの過程もあっさりとしています。
「大物浦」に転換します。。右額に血糊を塗る澤瀉屋型の知盛でした。蟹見得は省略でしたが、立ち廻りは流石團十郎という出来でした。義経が出てからは知盛の性根や入水に至る過程の描き方が弱く、感動に至りません。知盛の入水後に團十郎の弁慶が法螺貝を吹くのも1度のみであり、芝居の余韻がありません。
星空の背景で客席通路に電気の人魂を浮かべ、平家の女中が灯りを手にして舞います。知盛の亡霊が宙乗りで成仏するのですが、宙乗りをやっておけば見物客が喜ぶだろうという安易な考えが透けて見え、寧ろ興醒めでした。
「椎の木」では、團十郎が小金吾と権太の早替りのためすぐに小金吾が小せんと共に下手に引っ込み、本来登場しない志のぶの腰元が小金吾の代わりに権太の荷物を解いてしまい、権太に金20両を盗んだ疑いをかけられてしまいます。しかし、内侍と六代が鮨屋を訪れた際に腰元はおらず、小金吾同様に腰元も何処かで討死したのでしょうか。舞台転換を早くするためか椎の木に石を投げても実は落ちませんでした。
「小金吾討死」の立ち廻りは所作にキレがありました。権太や弥左衛門との早変わりのため仕方がないのですが、小金吾が白塗りではなく砥の粉なのが気になります。これは後の維盛でも同様です。
「鮨屋」の権太は江戸風であり、いかにも江戸っ子という團十郎のニンに合った権太でした。莟玉のお里には弥助への気持ちを表現する時間がありません。
詮議では弥左衛門が影になっているため梶原の前に銀を出す場面がありません。男女蔵の梶原平三が父譲りの堂々としていて見応えがありました。
弥左衛門が権太を刺す場面も、普通は背中から斬りかかってから腹を刺しますが、今回では暖簾や屏風を使って弥左衛門と権太の2役を團十郎が入れ替わりながら演じます。この弥左衛門、それではその後のモドリが出来ないだろうと思う位に権太を斬りつけます。二重から階に足を下ろして権太のモドリになり、維盛に早替わるため権太が早々に息を引き取ります。権太に笛を吹く体力はなく弥左衛門が吹きます。
「吉野山」の道行は全段カットで「四の切」になります。
本物の忠信は下緒を手繰る所作などが省略されておりすぐ上手に引っ込んでしまいます。
源九郎狐になってからは声が悪く気の抜けたような狐言葉であり、雀右衛門の静御前が安定した芝居をしているのに鼓の詮議の緊張感が途切れるようでした。鼓の子狐とはいえ桓武天皇の時代から400年近く生きており、妻子もいるのですから、源九郎狐はただの子狐ではいけないのです。その後も狐親子の情愛を示す場面が大幅に削られており、性根が薄く感じられました。
最近の澤瀉屋型では山法師の立ち廻りが長いように思います。元々山法師の立ち廻りは3代目猿之助が滅多に上演されない五段目の内容を取り入れた演出です。特に今回は五段目も上演するのですから、立ち廻りが続いてくどくなってしまいます。
源九郎狐の宙乗りになりますが、宙乗りに合わせて見物客が手拍子を叩いており、暗澹たる気分になりました。
五段目「蔵王堂花矢倉の段」では、佐藤忠信、横川覚範、武蔵坊弁慶、藤原朝方の4役を襖で隠れながら早替わりで勤めます。横川覚範実は平教経が佐藤忠信に討たれてから、スクリーンが降りてきて團十郎が演じた13役が上映されます。
切口上の際、屋根から雪が滑り落ちるように桜を降らせ3階席からもバズーカで桜を降らせるのは、風情がありません。
全体的に殺陣を残して性根を伝える場面を省略してしまったためにプロセスが不明瞭になり、派手な「歌舞伎らしい」事をしている演目となってしまっています。外国人や若い人には受けるのでしょうが、心を打たれません。

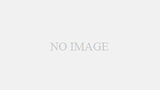

コメント